「if-else型条件文」
5章で学んだことの復習をしましょう。
<if文>
if文は、「条件によってAの処理をするかBの処理をするかを決める」というときに用いられます。「if-else型条件文」
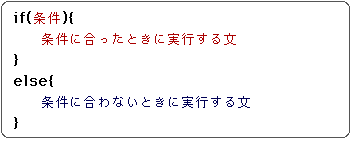
<else if文>
else if文というのは、条件が複数あるときに使います。「else if文(条件が3つあるとき)」
この場合、条件1〜3までが上から評価され、一致したところの文を実行し、else if文から抜けます。一致する条件がなかった場合else節が実行されますが、else節に書くものがなければ、実行文を省略できます。
<関係演算子>
関係演算子は、2つの値の大小関係や等値関係を判定するものです。
関係演算子をまとめると次のようになります。
※ =が1つだけでは「a=10; 」のような数値代入の意味になってしまうので、等しいということを表すには==とイコールを2つ続けて書く。
演算子 説明 記述例 記述の意味 > 大きい
if(a>10)
aが10より大なら
>= 大きいか等しい
if(a>=10)
aが10以上なら
< 小さい
if(a<10)
aが10より小なら
<= 小さいか等しい
if(a<=10)
aが10以下なら
== 等しい
if(a==10)
aが10なら
!= 等しくない
if(a!=10)
aが10でないなら
<論理演算子>
論理演算子は、条件文の条件式が2つ以上あるときに使うものです。
論理演算子をまとめると次のようになります。
演算子 説明 記述例 記述の意味 && 論理積
(かつ/and)if(x==2 && y==5)
xが2かつyが5なら
|| 論理和
(または/or)if(x==2 || y==5)
xが2またはyが5なら
! 否定
(でない/not)if(!(x==2 && y==5))
xが2かつyが5、でないなら